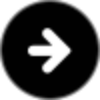インフルエンサーマーケティングのKPIツリー作成法|施策を成功に導く設計図
2025年10月06日

「今回の施策、コメントは盛り上がったけど、本当に成功…?」
「上司に『で、結局売上にどう貢献したの?』と聞かれ、答えに窮してしまった…」
企業のマーケティング担当者なら、このような経験があるかもしれません。インフルエンサーマーケティングは、ユーザーとの距離が近い分、成果が見えにくいことがあります。私もWebマーケティングを始めた頃は、「いいね」や「コメント」の数にばかり気を取られ、それが売上にどうつながるか説明できませんでした。
この不安の原因は、全体の計画がないまま、手探りで進めてしまうことです。地図も持たずに冒険に出ても、目的地にはたどり着けませんよね。
そこで役立つのが、「KPIツリー」です。これは、最終的な目標から逆算して、各施策がどう貢献するかを図で示す考え方です。KPIツリーがあれば、感覚的な評価に頼らず、データに基づいて自信を持って施策を進められます。
目次
1.最終目標(KGI)から逆算して考える
施策の成否は、始める前に「何を達成すれば成功か」を明確に定めることでほぼ決まります。この最終目標をマーケティング用語で「KGI(Key Goal Indicator)」と呼びます。
難しく感じるかもしれませんが、KGIは「施策で本当に達成したい、ビジネス上のたった一つの目標」のことです。例えば、以下のようなものがKGIになります。
- ECサイトの売上金額を前月比で120%にする
- 新商品の月間販売個数を5,000個にする
- サービスの新規無料会員登録者数を1ヶ月で1,000人獲得する
- 店舗への来店予約数をキャンペーン期間中に300件増やす
これらはすべて、会社の利益に直結する具体的な目標です。
以前、あるコスメブランドで「いいね!」を集めることに力を入れた結果、インフルエンサーの投稿は合計10万「いいね!」を獲得しました。しかし、売上はほとんど変わらず、目標設定がビジネスの最終目標からずれていたことが原因でした。
家を建てる時、完成図(KGI)があるからこそ、基礎工事や柱の位置(KPI)が決まります。いきなり現場で釘を打ち始める人はいませんよね。インフルエンサーマーケティングも同じです。
まず「ビジネスで何を達成したいか」を議論し、KGIをチームで共有することから始めましょう。
2.KGIを達成するための中間目標(KPI)を設定
KGIを決めたら、次は山頂への「チェックポイント」を設定していきます。これが「KPI(Key Performance Indicator)」、重要業績評価指標と呼ばれるものです。
KGIが「富士山の山頂に到達する」という最終目標だとしたら、KPIは「五合目に到達する」「八合目の山小屋に到着する」といった、ゴールへ向かうプロセスが順調に進んでいるかを確認するための中間目標です。これらのチェックポイントを一つひとつクリアしていくことで、私たちは初めて山頂にたどり着くことができます。
例えば、「ECサイトの売上を前月比120%にする」というKGIを掲げたとします。ECサイトの売上は、一般的に以下の式で分解できます。
売上 = サイト訪問者数 × 購入率(CVR) × 平均顧客単価
この式を元にすれば、KGIを達成するための中間目標、つまりKPIが見えてきます。
- KPI①:インフルエンサーの投稿経由のサイト訪問者数を〇〇人にする
- KPI②:サイト訪問者の購入率を〇%にする
- KPI③:平均顧客単価を〇〇円にする
このように、KGIを構成要素に分解していくことで、施策で具体的に何を追いかければ良いのかが明確になります。
ここで重要なのは、「良いKPI」と「悪いKPI」を見極めることです。
- 悪いKPIの例:「エンゲージメントを高める」「ブランドの認知を広げる」
これらは目標として正しいものの、達成基準が曖昧で測定が難しくなります。 - 良いKPIの例:「投稿後24時間以内の保存数を平均500件以上にする」「キャンペーンハッシュタグを付けたUGC(ユーザー投稿)を50件作る」
誰が見ても達成できたか判断できる、具体的で測定可能な指標が良いKPIです。
「SMART(スマート)」と呼ばれるフレームワークを使い、KPIの精度が上がります。
- Specific(具体的か)
- Measurable(測定可能か)
- Achievable(達成可能か)
- Relevant(KGIと関連性があるか)
- Time-bound(期限が明確か)
このフレームワークに沿って設定されたKPIは、チームメンバー全員の行動を具体的にし、施策の進捗を正確に測るための、信頼できる「道しるべ」となってくれるのです。
3.インフルエンサーの投稿がどう売上に繋がるか分解する
KGIとKPIの関係性が見えてきたら、次は「インフルエンサーの投稿が、一体どのようなプロセスを経て、最終的な売上(KGI)につながるのか?」を考えます。
この「分解」が、KPIツリーの骨格を作り上げる上で重要なプロセスとなります。顧客の行動を想像してみましょう。
例えば、女性がInstagramを見ているとします。
- 【投稿の発見】フォローしているインフルエンサーが素敵なワンピースを紹介。
- 【興味・関心】着心地のレビューに惹かれ、「いいね!」や「保存」をする。
- 【情報収集】ブランド名を調べ、プロフィールページへ移動。
- 【サイトへ移動】ECサイトへのリンクをタップ。
- 【商品ページの閲覧】ワンピースの価格や素材などの詳細を確認。
- 【カート追加】「欲しい!」と思い、商品をカートに入れる。
- 【購入完了】決済情報を入力し、購入する。
一つの「購入」の裏には、多くの顧客の行動が隠れています。インフルエンサーの投稿は、そのきっかけにすぎません。
過去のキャンペーンで、エンゲージメントは高いのに、ECサイトへの流入が全く増えない投稿がありました。原因は、インフルエンサーがURLへの誘導をしていなかったことでした。
この経験から、各ステップがスムーズにつながっているかを確認することの重要性を学びました。この顧客の行動ステップが、「各フェーズのKPI」を設定するための土台となります。
4.認知・興味・比較検討・購入の各フェーズのKPI
インフルエンサーの投稿が売上につながるまでの流れを分解したら、マーケティングのフレームワークに当てはめて、KPIを整理します。
顧客の購買行動は、一般的に「パーチェスファネル」というモデルで説明されます。これは、顧客が商品を認知してから購入に至るまでのプロセスを、漏斗(ファネル)の形に例えたものです。ここでは、シンプルに4つのフェーズに分けて考えてみましょう。
- 認知フェーズ:まずは「知ってもらう」段階
まだあなたのブランドや商品のことを知らない人に、その存在を届けるのが目的です。ここでは、どれだけ多くの人の目に触れたかが重要になります。- 主なKPI:インプレッション数、リーチ数、動画の再生数
- 興味・関心フェーズ:「いいね!」と思ってもらう段階
存在を知った人々に、あなたのブランドや商品に対してポジティブな感情を持ってもらい、もっと知りたいと思わせるのが目的です。投稿に対する反応の質と量が問われます。- 主なKPI:エンゲージメント数(率)、コメント数、保存数(「後で見返したい」という、より深い興味関心を示す指標)、プロフィールへのアクセス数
- 比較・検討フェーズ:「もっと詳しく知りたい」と思ってもらう段階
興味を持った人々が、購入を具体的に検討し始める段階です。あなたのサイトを訪れたり、他の商品と比較したりします。ブランドサイトへの誘導が成功しているかが鍵となります。- 主なKPI:URLクリック数(率)、サイト滞在時間、指名検索数、UGC(ユーザー生成コンテンツ)数
- 購入・行動フェーズ:最終的に「行動してもらう」段階
比較検討の結果、最終的に商品の購入やサービスの申し込みといった、ビジネス上のゴールとなる行動を起こしてもらうのが目的です。- 主なKPI:コンバージョン(CV)数、コンバージョン率(CVR)、クーポンコード利用数、来店数・予約数
これらのKPIは、先ほど分解した「売上までの道のり」の各チェックポイントを、測定可能な指標に置き換えたものに他なりません。施策の目的に応じて、どのフェーズのKPIを重視するかが変わってくるのです。

5.インフルエンサー選定やコンテンツもKPIツリーで管理
KPIツリーの素晴らしい点は、施策が「終わった後」の分析ツールとしてだけでなく、施策を「始める前」の計画ツールとしても絶大な威力を発揮することです。つまり、設定したKPIを達成するために、「誰に(インフルエンサー選定)」、「何を(コンテンツ企画)」話してもらうべきか、という施策の根幹を設計するための指針となるのです。
インフルエンサー選定への応用
もしあなたの施策の最重要KPIが「購入コンバージョン数」だとしましょう。その場合、インフルエンサーを選定する基準はどうなるでしょうか?
- ありがちな失敗:単純にフォロワー数が多い人や、知名度が高い人を選んでしまう。
- KPIツリー思考での選定:フォロワー数はそこまで多くなくても、過去のタイアップ投稿で高いURLクリック率やコンバージョン率を記録している人。あるいは、特定の商品カテゴリーにおいて、フォロワーから絶大な信頼を得ている「マイクロインフルエンサー」を重視する。
逆に、最重要KPIが「認知フェーズのリーチ数」であれば、とにかく多くの人に情報を届けられる拡散力の高いインフルエンサーを選ぶのが正解となります。目的(KPI)が明確だからこそ、選定基準がブレなくなるのです。
コンテンツ企画への応用
同様に、企画するコンテンツ内容も、どのKPIを重視するかによって大きく変わります。
- 「保存数」をKPIにする場合:
「何度も見返したくなる情報」が求められます。例えば、「着回し7daysコーデ」「シーン別メイク術まとめ」のような、実用的なノウハウ系のコンテンツが有効です。 - 「コメント数」をKPIにする場合:
ユーザーとのコミュニケーションを誘発する仕掛けが必要です。「皆さんはどっちの色が好きですか?」のように、投稿の最後に問いかけを入れることで、コメント欄が活性化しやすくなります。 - 「URLクリック数」をKPIにする場合:
投稿の中で、いかに自然かつ魅力的に「続きはWebで」という流れを作れるかが鍵になります。商品の魅力をすべて語り尽くすのではなく、「この秘密はサイトで公開中」のように、あえて情報の一部を隠して好奇心を煽るテクニックも効果的です。
私が担当したある案件では、KPIを「保存数」に設定し、インフルエンサーの方には徹底的に「まとめ情報」に特化したコンテンツ作成を依頼しました。結果、いいね!の数は平均的でしたが、保存数は他の投稿の5倍以上を記録。この投稿は一過性のバズで終わらず、キャンペーン終了後も数ヶ月にわたってユーザーの保存リストから参照され続け、結果的にサイトへの継続的な流入を生み出す「資産」のようなコンテンツになりました。
このように、KPIツリーは、インフルエンサー選定とコンテンツ企画という、施策の成否を分ける二大要素の「判断軸」そのものになってくれるのです。
6.施策全体の関係性を可視化する
KPIツリーを作成する最大のメリットは、これまで頭の中にぼんやりと存在していた施策の全体像を、誰の目にも明らかな形で「可視化」できる点にあります。
このツリーは、文字通り「木」のような構造をしています。
- 【幹】:KGI(最終目標)
- 【太い枝】:KGIを達成するための中間目標(KPI)
- 【細い枝や葉】:KPIを達成するための具体的なアクションプラン
この一本の木を描くことで、これまでバラバラの点に見えていた各指標やアクションが、すべて最終目標という幹に繋がっていることが論理的に理解できるようになります。この「可視化」がもたらすメリットは計り知れません。
- 施策の全体像が一目でわかる
- 各指標の繋がりが論理的に理解できる
- チームメンバーや上司への説明が容易になる
- 「なんとなく」から構造的な思考へシフトできる
面白いことに、私がKPIツリーを導入してからというもの、マーケティング部門以外の営業部門や経営層からも、施策への理解が格段に得やすくなりました。「なるほど、君たちがやっているインスタの投稿は、最終的に会社のこの数字のためにあるんだね」と。部門間の壁を越えて、施策の目的がスムーズに共有されるようになったのは、予想外の嬉しい効果でしたね。
施策に関わる全員が同じ「設計図」を見ながら会話をする。この状態を作り出すことこそが、組織としてインフルエンサーマーケティングを成功させるための、重要な土台となるのです。
7.ボトルネックを発見し、改善策を打つ
KPIツリーという名の精密な「設計図」を手に入れたあなたは、もはや施策の結果に一喜一憂するだけの傍観者ではありません。問題の根本原因を特定し、的確な改善策を打てる、いわば「施策のドクター」になることができます。
KPIツリーは、施策の「健康診断の結果」に例えることができます。各KPIの目標値と実績値を比較していくことで、どの部分が健康で、どの部分に問題(=目標未達)があるのかが一目瞭然になります。この、全体の流れを滞らせている根本原因のことを「ボトルネック」と呼びます。
具体的な事例をいくつか見てみましょう。
- 事例1:「認知」は取れているが、「興味」に繋がらないケース
- データ:インプレッション数(認知KPI)は目標を大幅に達成。しかし、URLクリック数(比較検討KPI)が全く伸びていない。
- ボトルネックの特定:投稿自体は多くの人に見られているが、内容に魅力がなく、サイトへ行きたいと思わせる力が弱い。あるいは、サイトへの導線設計に問題がある。
- 考えられる改善策:
- インフルエンサーの投稿クリエイティブを見直す。
- プロフィールやストーリーズからのURLへの誘導を強化する。
- 起用するインフルエンサーのファン層と、商品のターゲット層が本当に合っているか再検証する。
- 事例2:「サイト流入」は多いが、「購入」に繋がらないケース
- データ:URLクリック数は目標を達成し、多くのユーザーがサイトを訪れている。しかし、購入率(CVR)が極端に低い。
- ボトルネックの特定:インフルエンサーの投稿内容は魅力的だったが、遷移先のランディングページ(LP)に問題がある。
- 考えられる改善策:
- ランディングページを改善する。(インフルエンサーの投稿内容とLPのトンマナを合わせる、購入ボタンを分かりやすくするなど)
- インフルエンサーの選定基準を見直す。
- 初回購入限定の割引クーポンを提供するなど、購入へのハードルを下げる施策を追加する。
このように、KPIツリーがあれば、問題が発生した時に「どこに戻って、何を修正すれば良いか」が明確になります。闇雲に「もっと頑張ろう」と精神論に走るのではなく、データに基づいて具体的な打ち手を考え、実行し、また結果を測定する。このPDCAサイクルを高速で回していくことができる。これこそが、KPIツリーを持つマーケターの最大の強みなのです。
8.データに基づいたインフルエンサーマーケティング
これまで解説してきたことを実践すると、あなたのインフルエンサーマーケティングは、「感覚」や「個人のセンス」に依存した属人的なものから、「データ」という客観的な事実に基づいて意思決定を行う、科学的なアプローチへと進化します。
これまでの曖昧な評価基準は、もう必要ありません。
- 【Before】
「インフルエンサーのAさんの投稿、すごくバズったから大成功だったね!」 - 【After】
「Aさんはリーチ数が圧倒的に多く、新規顧客への認知獲得というKPI達成に大きく貢献してくれた」
このように、各インフルエンサーが施策全体のどの部分で、どのような役割を果たし、どれだけの成果を上げたのかを、データに基づいて明確に評価できるようになります。
この評価データは、次回の施策を計画する上で、何物にも代えがたい貴重な資産となります。
- 予算配分の最適化
どのフェーズのKPIに、どのインフルエンサーが強いのかが分かれば、次回の予算をより効果の高いインフルエンサーやコンテンツに重点的に投下できます。 - インフルエンサーとの関係構築
施策への貢献度が高いとデータで証明されたインフルエンサーとは、より長期的で強固なパートナーシップを築くべきだという判断ができます。 - 施策の再現性の向上
なぜ成功したのか、なぜ失敗したのかをデータで語れるため、成功の要因を他の施策にも横展開したり、失敗の要因を回避したりすることが可能になります。
もちろん、マーケティングにおいて、長年の経験からくる「勘」や、トレンドを捉える「センス」が重要であることは言うまでもありません。しかし、その勘やセンスを裏付ける客観的なデータを持つことで、あなたの提案は圧倒的な説得力を持ち、施策の成功確率は飛躍的に高まります。
データは時に、目を背けたくなるような厳しい現実を突きつけてくることもあります。しかし、その声に真摯に耳を傾けることこそが、あなたのマーケティングを本質的な成長へと導く、唯一の道なのです。

9.チームで目標を共有するためのツール
KPIツリーは、個人のマーケターが施策を管理するためのツールに留まりません。むしろ、チームや組織全体の目線を合わせ、同じゴールに向かって力を結集させるための、強力なコミュニケーションツールとしての側面を持っています。
考えてみてください。サッカーの試合で、監督が「とにかく点を取ってこい!」とだけ指示したとしたら、選手たちはどう動いて良いか分からず、バラバラにプレーしてしまうでしょう。優れた監督は、「まずサイドバックがここまでボールを運び、そこからセンターフォワードへクロスを上げる」というように、勝利(KGI)から逆算した具体的な戦術(KPIとアクションプラン)をチーム全員に共有します。
KPIツリーは、まさにこの「戦術ボード」の役割を果たします。
- 役割分担が明確になる
ツリーを見ることで、チーム内の誰がどのKPIに責任を持つのかが一目瞭然になります。 - 目標に対する認識のズレがなくなる
全員が同じKPIツリーという「設計図」を見ている状態であれば、「今回の施策のゴールは売上だ」「いや、まずは認知度アップが最優先だろう」といった不毛な対立は起こり得ません。 - 上司や他部署への「説明コスト」が劇的に下がる
「なぜ、この施策にこれだけの予算が必要なのですか?」といった問いに対して、KPIツリーを提示すれば、すべての活動が最終的なビジネスゴールにどう繋がっているのかを、誰にでも論理的に説明できます。
私が以前所属していたチームでは、KPIツリーを会議のアジェンダの中心に据えるようになってから、明らかに議論の質が変わりました。「誰のせいだ」といった犯人探しのための会話が消え、「このKPIが未達だが、どうすれば達成できるか?」という、課題解決に向けた建設的で前向きな会話が圧倒的に増えたのです。これは、チームの心理的安全性をも高める、素晴らしい効果でした。
KPIツリーは、チームの共通言語。組織の力を最大化するための、最強のツールなのです。
10.戦略的なインフルエンサー施策の第一歩
ここまで、KPIツリーの作成法とその絶大な効果について解説してきました。もしかしたら、「なんだか難しそうだな」「完璧なツリーなんて作れるだろうか」と感じた方もいるかもしれません。
しかし、心配する必要は全くありません。最初から、全ての指標を網羅した完璧なツリーを目指す必要はないのです。大切なのは、KGI(最終目標)から逆算して施策を構造的に捉えようとする、「思考のクセ」を身につけることです。
まずは、あなたの次のキャンペーンで、手元にある紙とペンを用意して、簡単なものからで良いのでツリーを描いてみてください。
- 一番上に、最終目標(例:売上〇〇円)を書く。
- その下に、それを達成するために必要だと思う中間目標(例:サイト訪問者数、購入率)をいくつか書き出す。
- さらにその下に、中間目標を達成するための具体的なアクション(例:インフルエンサーAさんを起用)をぶら下げてみる。
たったこれだけでも、あなたの頭の中は驚くほど整理されるはずです。そして、その手書きのツリーをチームメンバーに見せてみてください。「ここの繋がりは、もっとこう考えた方が自然じゃない?」「このアクションなら、こっちのKPIにも貢献できそうだね」といった会話が生まれ、ツリーはどんどん洗練されていくでしょう。
インフルエンサーマーケティングは、単発の花火を打ち上げるような広告宣伝活動ではありません。インフルエンサーやその先にいるファンコミュニティと真摯に向き合い、共にブランドを育てていく、長期的で継続的な取り組みです。
その長い航海において、KPIツリーは、嵐の中でも進むべき方向を見失わないための、信頼できる羅針盤となってくれます。この羅針盤を手に、データに基づいた戦略的な施策への第一歩を、今日から踏み出してみませんか。

「設計図」があれば、インフルエンサーマーケティングはもっと面白くなる
インフルエンサーマーケティングの効果測定が曖昧で、成果をどう評価すれば良いか分からない。そんな多くのマーケターが抱える深い悩みは、施策全体の「設計図」を持たないまま進んでいることに起因します。
KPIツリーという設計図は、その名の通り、あなたの施策に明確な構造と論理的な繋がりを与えてくれます。
- まず、最終ゴールであるKGIを明確に定めること。
- 次に、ゴールから逆算して、各フェーズで達成すべきKPIを設定すること。
- そして、そのツリーを元に、施策のボトルネックを発見し、データに基づいて改善を繰り返すこと。
このプロセスを実践することで、あなたは「なんとなく」の不安から解放され、自信を持って施策を推進できるようになります。KPIツリーは、チームの目線を合わせ、上司や経営層を説得し、組織全体を動かすための強力な武器にもなり得ます。
まずは、あなたの次のキャンペーンで、紙とペンを用意して、自分だけのKPIツリーを描いてみることから始めてみてください。
その一本の線、一つの箱が、あなたのインフルエンサーマーケティングを感覚的なものから戦略的なものへと進化させ、未来の大きな成功へと繋がる、確かな第一歩となるはずです。