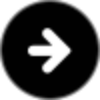MEOとは?店舗集客の基本を初心者向けに徹底解説
2025年10月24日

「最近、近所のライバル店がGoogleマップでやたらと目立つ位置にいる…」 「スマートフォンで『近くのカフェ』と検索して来店してくれるお客さんを、もっと効率的に集めたい」
地域に根差した店舗を経営されているあなたなら、今、こんな風に感じているかもしれません。Webでの集客が重要だと頭では分かっていても、「何から手をつけていいか分からない」というのが本音ではないでしょうか。私自身、Webマーケティングのコンサルタントとして、多くの熱意ある店舗オーナーの方々から、そうした切実なご相談を数えきれないほど受けてきました。
そんな数あるWeb集客手法の中で、特に実店舗を構えるビジネスにとって、最も即効性が期待でき、費用対効果も抜群に高いのが「MEO」です。MEOは、難しい専門知識や多額の広告費がなくても、正しい知識と少しの手間さえかければ、誰でも始めることができます。これから、MEOという言葉を初めて聞いたという初心者の方でも、その重要性から具体的な始め方、最低限知っておくべき専門用語まで、全てを分かりやすく解き明かしていきます。
目次
1. MEOが今、注目される理由
なぜ今、これほどまでに「MEO」という言葉が、店舗ビジネスの世界で重要視されているのでしょうか。その背景には、私たちの情報収集の仕方を根底から変えた、3つの大きな時代の変化があります。
- スマートフォンの爆発的な普及 今や、誰もが手のひらの上に「高性能なパソコン」を持っている時代です。そして、私たちは何かを知りたい時、特に「どこかへ行きたい」「何かを食べたい」と思った時、その場で即座にスマートフォンを取り出し検索します。この「今いる場所から、近くのお店を探す」という行動が日常化したことこそが、MEOが注目される最大の理由です。顧客は、もはや家のパソコンでじっくりお店を探すのではなく、街を歩きながら、次の目的地を決めているのです。
- Google検索結果の画面の変化 試しに今、あなたのスマートフォンで「広島駅 カフェ」と検索してみてください。おそらく、通常のウェブサイトの一覧が表示されるよりも上に、まず大きな地図と、その下に3つの店舗情報が表示されているはずです。これは「ローカルパック」と呼ばれ、ユーザーの目に最も留まりやすい、いわば検索結果の一等地です。この一等地に自分のお店を表示させるための対策こそがMEOであり、その注目度は日に日に高まっています。
- 消費者の口コミに対する価値観の変化 かつて、お店選びの参考にする情報源といえば、グルメ情報サイトなどが主流でした。しかし近年、多くのユーザーが最も信頼する情報源として活用しているのが、Googleマップに投稿された一般ユーザーの「口コミ」です。やらせや広告ではない、リアルな顧客の声が、新しい顧客を呼び込む上で絶大な力を持つようになっています。
私が以前コンサルティングを担当したある地方都市のイタリアンレストランは、当初、広告費をかけてグルメサイトに掲載していましたが、思うように新規顧客が増えずに悩んでいました。そこで、広告費をゼロにして、その分の労力をMEO対策、特に口コミの管理と情報発信に集中させたのです。その結果、わずか半年で広告費をかけずに新規の来店客数を前年比で130%にまで伸ばすことに成功しました。これは、現代の顧客がどこで情報を探し、何を信じてお店を選んでいるかを如実に示す事例と言えるでしょう。
2. SEOとMEOの根本的な違いとは
Web集客の話になると、必ずと言っていいほど登場するのが「SEO」と「MEO」という二つの言葉です。これらはアルファベットが一つ違うだけなので、非常に混同されやすいのですが、その目的も戦う場所も、実は全く異なります。初心者の方がつまずかないよう、たとえ話を交えながら、その根本的な違いを解説します。
- SEO (Search Engine Optimization) とは? SEOを一言でいうと、自社のウェブサイト(ホームページ)を、Googleなどの検索結果で1ページ目や1位といった、できるだけ上位に表示させるための対策全般を指します。
- 目的: ウェブサイトへのアクセスを増やすこと。
- 戦う場所(キーワード): 「ラーメン レシピ」「肩こり 原因」といった、地域を限定しない広域なキーワードが主戦場です。
- たとえ話: SEOは、いわば「全国規模の料理コンテスト」で優勝を目指すようなものです。日本中のライバルと、その料理の質(ウェブサイトの質)を競い合います。
- MEO (Map Engine Optimization) とは? 一方、MEOは、Googleマップ上での検索結果において、自社の店舗情報を上位に表示させるための対策に特化したものです。「ローカルSEO」と呼ばれることもあります。
- 目的: 店舗への来店を促すこと。
- 戦う場所(キーワード): 「渋谷 ラーメン」「新宿 肩こり マッサージ」といった、「地域名+業種・サービス名」が主戦場です。
- たとえ話: MEOは、「渋谷区のラーメン人気ランキング」で1位を目指すようなものです。戦う相手は全国のラーメン店ではなく、あくまで渋谷区内にある近所のライバル店です。
このように、SEOが全国のライバルと戦う空軍だとしたら、MEOはご近所のライバルと戦う地上軍のようなイメージです。実店舗ビジネスにとっては、まず自分の足元である地域で圧倒的な一番になることが重要であり、そのためにMEOは極めて強力な武器となります。
もちろん、両者は無関係ではありません。MEO対策であなたのお店に興味を持った顧客が、さらに詳しい情報を求めてウェブサイトを訪れることもあります。最終的には、MEOとSEOが連携し合うことで、集客効果を最大化できるという点も覚えておくと良いでしょう。
3. Googleマップで上位表示されるメリット
MEO対策に時間と労力をかけることで、あなたのビジネスには具体的にどのような恩恵がもたらされるのでしょうか。ここでは、Googleマップで上位表示されることの絶大なメリットを5つご紹介します。
- 来店に直結する意欲の高い顧客に届く 最大のメリットは、何と言ってもその集客の質の高さです。「渋谷 ランチ」や「近くの 本屋」と検索しているユーザーは、ただ情報を知りたいだけではありません。「今から、あるいは今日中に、その場所へ行きたい」という、非常に明確な行動意欲を持っています。MEOは、こうした”今すぐ客”に、あなたのお店の存在を直接アピールできるため、他のどんな広告よりも来店に結びつきやすいのです。
- 地図や写真で視覚的に魅力を伝えられる 文字情報が中心のウェブ検索とは異なり、マップ検索では、お店の場所が地図上にピンで表示され、一目瞭然です。さらに、美味しそうな料理の写真、清潔感のある店内、スタッフの笑顔といった画像を豊富に掲載することで、顧客は来店する前に、お店の雰囲気をリアルに感じ取ることができます。この視覚的なアピールは、顧客の「行ってみたい」という気持ちを強く後押しします。
- 費用対効果が非常に高い MEO対策の中心となる「Googleビジネスプロフィール」の登録や運用は、なんと完全に無料で始められます。もちろん、専門の業者に対策を依頼すれば費用はかかりますが、基本的な設定や情報更新は、オーナー自身が少し勉強すれば十分に行うことが可能です。チラシやウェブ広告のように、継続的なコストをかけずに始められる点は、特に中小規模の店舗にとって大きな魅力と言えるでしょう。
- 地域の競合と効果的に差別化できる あなたの周りにあるライバル店を思い浮かべてみてください。その全てが、MEO対策に本格的に取り組んでいるでしょうか。おそらく、まだ多くの店舗がその重要性に気づいていないか、対策が不十分なはずです。MEOにいち早く、そして真剣に取り組むことで、地域内での競争において、大きなアドバンテージを築くことができます。
- 情報の信頼性が向上する Googleマップには、正確な営業時間や電話番号、そして多くのユーザーからの正直な口コミが集まっています。これらの情報がきちんと整備されているお店は、顧客に「ちゃんと運営されている、信頼できるお店だ」という安心感を与えます。好意的な口コミが増えれば、それは何よりも雄弁な広告塔となるのです。
4. どんなビジネスがMEO対策に向いているか
MEO対策は、特定の業種だけのものではなく、顧客が「地域名+業種名」で検索する可能性のある、実店舗を持つすべてのビジネスにとって、極めて有効な集客手段です。もし、あなたのお店が以下のいずれかに当てはまるなら、今すぐMEO対策を始めるべきと言えるでしょう。
- 飲食店 カフェ、レストラン、居酒屋、ラーメン店、パン屋、バーなど、MEOの恩恵を最も受けやすい代表的な業種です。「渋谷 ランチ」「新宿 居酒屋 個室」といった検索に、日々多くの見込み客が潜んでいます。
- 美容・健康関連 美容室、ネイルサロン、エステサロン、リラクゼーション、整体院、整骨院、歯科、クリニックなど。これらのお店は、定期的に通う顧客も多く、近所で信頼できるお店を探しているユーザーに的確にアプローチできます。
- 小売店 アパレルショップ、雑貨店、書店、花屋、スーパーマーケット、ドラッグストアなど。「近くの 〇〇」で検索されることが非常に多く、MEO対策が直接的な来店と購買に繋がります。
- 各種サービス業 クリーニング店、靴やカギの修理店、不動産会社、学習塾、英会話教室、フィットネスジム、ホテルなど。地域に根差したサービスを提供しているビジネス全般に有効です。
- 出張型のサービス ハウスクリーニングや水道修理、リフォーム業者など、明確な店舗はないものの、特定のエリア内でサービスを提供しているビジネスもMEOの対象となります。この場合、店舗の住所ではなく、対応可能なサービスエリアを設定することで、その地域内のユーザーにアピールできます。
逆に言えば、実店舗を持たず、オンライン上ですべてのサービスが完結するビジネスや、日本全国を対象とした通販サイトなどは、MEOの優先順位は低いと言えます。そうしたビジネスの場合は、地域を限定しないキーワードで戦う「SEO」に注力する方が、より効果的です。
あなたのビジネスが、地域のお客様に来てもらうことで成り立っているのなら、MEOはもはや「やってもやらなくても良い」選択肢ではなく、「必ずやるべき」必須の集客戦略なのです。

5. 対策を始める前の必須準備リスト
「よし、MEOの重要性は分かった。早速始めてみよう!」 その意気込みは素晴らしいですが、闇雲にスタートする前に、いくつか準備しておくべきことがあります。事前にこれらの情報を整理しておくことで、登録作業がスムーズに進み、より効果的なMEO対策のスタートを切ることができます。
ここでは、対策を始める前に必ず揃えておきたい「必須準備リスト」をご紹介します。
- Googleアカウントの用意 MEO対策の土台となる「Googleビジネスプロフィール」を管理するために、Googleアカウントが必須です。Gmailなど、普段お使いのもので構いません。もし持っていない場合は、無料で簡単に作成できます。
- 店舗の基本情報(NAP情報)の統一 これは非常に重要なポイントです。以下の3つの情報は、全ての媒体(ウェブサイト、SNS、各種情報サイトなど)で、一字一句違わぬように統一してください。
- N (Name): 店舗の正式名称
- A (Address): 店舗の住所(ビル名や階数まで正確に)
- P (Phone): 店舗の電話番号 例えば、「株式会社」と「(株)」、「1-2-3」と「1丁目2番地3号」といった表記の揺れは、Googleからの評価を下げる原因になり得ます。これを機に、自社の正式な表記を決定し、統一しましょう。
- ビジネスカテゴリの選定 Googleビジネスプロフィールでは、あなたのお店が何のビジネスなのかを示す「カテゴリ」を設定します。「イタリアンレストラン」「美容室」「歯科医院」など、Googleが用意した選択肢の中から、自店に最も近いものをメインカテゴリとして選びます。事前に、競合店がどのようなカテゴリを設定しているか調べておくのも良いでしょう。
- 魅力が伝わる写真の準備 写真は、MEOにおいて顧客の心を掴むための最強の武器です。プロのカメラマンに頼む必要はありません。今のスマートフォンのカメラは非常に高性能です。以下の写真を、それぞれ複数枚ずつ用意しておきましょう。
- 外観: お店の入り口が分かる、明るい写真。
- 内観: 店内の雰囲気が伝わる写真。
- 商品・サービス: 看板メニューの料理、施術の様子、人気商品など。
- スタッフ: スタッフが笑顔で働いている様子の写真(顧客に安心感を与えます)。
- 店舗の説明文の作成 お店の特徴や歴史、こだわり、どんなお客様に来てほしいか、といった情報をまとめた紹介文(750文字以内)をあらかじめ作成しておきましょう。ここには、顧客が検索しそうなキーワード(例:「個室あり」「深夜営業」など)を自然に盛り込むと、より効果的です。
これらの準備を万端に整えておくことが、MEO成功への確かな第一歩となります。
6. Googleビジネスプロフィールの重要性
MEO対策について語る上で、絶対に避けて通れないのが「Googleビジネスプロフィール(GBP)」の存在です。もし、MEO対策が店舗集客という名の壮大な演劇だとしたら、Googleビジネスプロフィールは、その脚本家であり、演出家であり、そして主役でもある、まさに中心的な存在です。
多くの方が、GBPを「Googleマップにお店の情報を載せるためだけの、単なる登録ツール」だと誤解していますが、それは大きな間違いです。現代のGBPは、もはやそれだけではありません。いわば、「Googleという巨大なプラットフォーム上に無料で持てる、自社の公式ホームページ」のようなものだと考えてください。
この強力なツールを使いこなすことで、あなたは顧客に対して様々な情報を発信し、コミュニケーションを取ることができます。
- 店舗の基本情報をリアルタイムで更新: 急な営業時間の変更や臨時休業など、最新の情報を即座に顧客に伝えることができます。
- 写真や動画を無制限に投稿: 新しいメニューや商品の写真、店内の雰囲気を伝える360°ビューの写真などを投稿し、お店の魅力を視覚的にアピールし続けられます。
- 「投稿」機能で最新情報を発信: キャンペーンの告知、イベントの案内、季節限定商品の紹介など、ブログやSNSのようにタイムリーな情報を発信できます。
- 顧客からの口コミに返信する: 良い口コミには感謝を、厳しいご意見には真摯な姿勢を示すことで、顧客との信頼関係を築き、他のお客様にも誠実な印象を与えます。
- ユーザーからの質問に回答する: 「駐車場はありますか?」といった顧客からのQ&Aに、オーナーとして公式に回答することができます。
- パフォーマンスを分析する: 管理画面の「インサイト」機能を使えば、自分の店舗がどのようなキーワードで検索されたか、何人のユーザーが電話をかけてきたり、ルートを検索したりしたか、といった貴重なデータを分析できます。
私が以前支援したある美容室の例では、このGBPの「投稿」機能を活用し、毎週、最新のヘアスタイル写真と簡単な解説を投稿し続けました。すると、それを見た新規の顧客から「この写真の髪型にしてください」という具体的な指名予約が入り始めたのです。
Googleビジネスプロフィールは、ただ登録して終わり、ではありません。情報を常に最新に保ち、積極的に活用することで初めて、MEO対策の司令塔として、その真価を発揮するのです。
7. MEOの基本的な仕組みを理解しよう
MEO対策を効果的に進めるためには、Googleがどのような考え方で、マップ上の店舗の表示順位を決めているのか、その基本的な「アルゴリズム」の仕組みを理解しておくことが重要です。
しかし、心配する必要はありません。複雑なプログラムの話を理解する必要は全くありません。覚えておくべき大原則は、たった一つです。
「Googleは、検索したユーザーにとって、最も関連性が高く、有益な店舗を、順番に表示したい」
Googleの使命は、ユーザーが抱える疑問やニーズに対して、最高の答えを提供することです。あなたが「新宿 焼肉」と検索した時、Googleはあなたに、新宿にある最高の焼肉店を教えたい、と考えています。その「最高」を判断するために、Googleは主に以下の3つの要素を見ている、と公式に発表しています。
- 関連性 (Relevance) これは、ユーザーが検索したキーワードと、あなたのお店の情報が、どれだけ一致しているか、という指標です。あなたが「新宿 焼肉」と検索した場合、Googleは「焼肉店」というビジネスカテゴリに登録されていて、店舗情報に「焼肉」や「新宿」という言葉が含まれているお店を、関連性が高いと判断します。
- 距離 (Distance) これは、言葉の通り、検索したユーザーの現在地(または検索時に指定した場所)から、お店までの物理的な距離です。当然ながら、より近くにあるお店の方が、ユーザーにとって利便性が高いと判断され、上位に表示されやすくなります。これは、MEOが「ご近所さん」を探すためのツールであることの証明でもあります。
- 知名度 (Prominence) これは、あなたのお店が、オンライン・オフラインを含めて、どれだけ「有名」で「広く知られている」か、という指標です。ホテルやランドマークのような、誰もが知っている有名な場所が上位に表示されやすいのは、このためです。
MEO対策とは、つまるところ、この「関連性」「距離」「知名度」という3つの評価軸に対して、自分のお店がいかに優れているかを、Googleに正しく、そして分かりやすく伝えてあげるための一連の活動、と言うことができるのです。
8. 上位表示に影響を与える3つの主要因
前のセクションで解説したMEOの基本的な仕組みである「関連性」「距離」「知名度」。ここでは、それらの評価を高めるために、私たちが具体的にどのようなアクションを取るべきなのかを、さらに詳しく掘り下げていきます。
- 「関連性」を高めるためのアクション Googleに「このお店は、このキーワードと深く関連していますよ」と伝えるためには、Googleビジネスプロフィールの情報を徹底的に充実させることが最も重要です。
- 正確なカテゴリ設定: あなたのビジネスを最も的確に表すメインカテゴリと、関連するサブカテゴリを設定しましょう。(例:メイン「イタリアンレストラン」、サブ「ピザ」「パスタ」)
- 情報の網羅性: 店舗名、住所、電話番号はもちろん、営業時間、ウェブサイト、提供している商品やサービス、お店の説明文など、入力できる項目はすべて、丁寧に埋めてください。
- キーワードの適切な配置: 説明文や投稿、商品・サービスの説明の中に、ユーザーが検索しそうなキーワード(例:「個室」「飲み放題」「テイクアウト」など)を、不自然にならないように盛り込みましょう。
- 口コミの内容: ユーザーが投稿してくれる口コミの中に、キーワードが含まれていると、Googleはそれを「このお店は、このキーワードに関連する体験を提供している」と判断し、評価を高めます。
- 「距離」という変えられない要素への考え方 ユーザーとお店との物理的な距離は、私たち自身がコントロールできるものではありません。しかし、悲観する必要はありません。ユーザーの検索行動は多様化しています。
- 例えば、新宿にいるユーザーが「ラーメン」と検索すれば、現在地から最も近いお店が表示されやすいでしょう。
- しかし、「新宿西口 ラーメン 家系」のように、より具体的で詳細なキーワードで検索した場合、たとえ少し距離が離れていても、その条件に最もマッチする「関連性」の高いお店が上位に表示される可能性があります。
つまり、距離で劣る分は、他の要素、特に「関連性」や「知名度」でカバーするという戦略が可能なのです。
- 「知名度(視認性の高さ)」を高めるためのアクション お店の有名度を上げるには、オンラインとオフラインの両面からのアプローチが必要です。
- 口コミの数と評価(スコア): MEOにおいて最も重要な要素の一つです。好意的な口コミが多く、評価の星の平均点が高いお店は、Googleから「人気があり、信頼できるお店」と判断されます。来店客に口コミの投稿を丁寧にお願いする、投稿された口コミに誠実に返信する、といった地道な努力が実を結びます。
- ウェブサイトやSNSでの言及(サイテーション・被リンク): あなたのお店のウェブサイトが、他の有名なサイトやブログ、SNSで紹介される(リンクが貼られる)と、Googleは「このお店は、外部からも注目されている有名店だ」と認識します。
- オフラインでの評判: 長年地域で愛されている老舗や、雑誌・テレビで紹介されたお店が評価されやすいように、オンライン上だけでなく、現実世界での人気や評判も、巡り巡ってMEOの評価に影響します。
結局のところ、小手先のテクニックだけでなく、お客様に愛され、良い評判が自然と広まるような、魅力的なお店作りそのものが、最強のMEO対策となるのです。

9. 自店舗の現状順位を確認する方法
MEO対策という長い旅に出る前に、まずは自分のお店の「現在地」を正確に知ることが不可欠です。つまり、特定のキーワードで検索した時に、自分のお店がGoogleマップ上で何位に表示されるのかを把握するのです。
「それなら簡単、いつも通りスマホで検索すればいいんでしょ?」 そう思った方は、注意が必要です。実は、あなたが普段何気なく行っている検索では、正確な順位を知ることはできません。
なぜなら、Googleの検索結果は「パーソナライズ」されているからです。これは、あなたの過去の検索履歴、閲覧したウェブサイト、そして何より「今いる場所」といった個人的な情報に基づいて、あなたにとって最も便利だと思われる結果を、Googleが自動的に表示する仕組みです。例えば、あなた自身が自分のお店に何度もアクセスしていれば、Googleは「この人は、このお店がお気に入りなんだな」と判断し、実際の実力以上に上位に表示させてしまうことがあるのです。
では、どうすれば客観的で正確な順位を確認できるのでしょうか。主な方法は2つあります。
- ブラウザの「シークレットモード」を利用する Google Chromeなどのウェブブラウザに搭載されている「シークレットモード(プライベートブラウジング)」を使えば、あなたの過去の履歴に影響されない、比較的まっさらな状態の検索結果を見ることができます。このモードでGoogleマップを開き、調べたいキーワード(例:「広島駅 居酒屋」)で検索することで、より客観的な順位が確認できます。
- MEO順位チェックツールを利用する さらに正確な順位を知りたい、あるいは、特定の場所からの見え方を確認したい場合には、専用のツールを使うのがおすすめです。これらのツールを使えば、「広島駅前から検索した場合」と「紙屋町から検索した場合」とでは、順位がどう変わるか、といった商圏内の様々な地点からの順位をシミュレーションすることができます。無料でも利用できるツールがいくつか存在するので、一度試してみる価値はあります。
MEO対策は、一度やって終わりではありません。定期的に順位をチェックし、「この施策を行ったら順位が上がった」「ライバル店がこんな対策を始めたから順位が下がった」といったように、効果測定と改善を繰り返していくことが、成功への唯一の道なのです。
10. 最低限これだけは押さえたいMEO用語集
これからMEOについて、さらに情報を集めたり、専門家と話したりする上で、必ずと言っていいほど登場する基本的な専門用語があります。ここでは、初心者の方がつまずかないように、最低限これだけは知っておきたい用語を厳選し、分かりやすく解説します。
- Googleビジネスプロフィール (GBP) MEO対策を行うための、最も重要で中心的な管理ツールのこと。以前は「Googleマイビジネス」という名称でした。お店の基本情報や写真の登録、口コミへの返信など、MEOに関するあらゆる操作は、この管理画面から行います。
- ローカル検索 「地域名+キーワード」(例:「渋谷 カフェ」)のように、特定の地域に関する情報を探す目的で行われる検索のこと。Googleマップ上での検索も、このローカル検索に含まれます。
- ローカルパック Googleの検索結果ページで、通常のウェブサイト一覧よりも上部に表示される、地図と3つの店舗情報がセットになった表示枠のこと。この3枠以内に入ることが、MEO対策の当面の目標となります。
- NAP情報 (ナップ情報) お店のName(名前)、Address(住所)、Phone(電話番号)の3つの基本情報の頭文字を取った言葉。このNAP情報を、ウェブサイトやSNSなど、全ての媒体で一字一句同じ表記に「統一」することが、MEOの基本中の基本です。
- サイテーション あなたの店舗のNAP情報が、他のウェブサイトやブログ、SNSなどで「言及」されること。例えば、地域の情報サイトにあなたのお店の情報が掲載されると、それは1つのサイテーションとしてカウントされます。このサイテーションが多いほど、お店の知名度が高いとGoogleに認識されやすくなります。
- インサイト Googleビジネスプロフィールの管理画面内で確認できる、無料の分析データのこと。ユーザーがあなたのお店をどのようなキーワードで見つけたか、何人が電話をかけ、何人がウェブサイトを訪れたか、といったパフォーマンスを具体的な数値で把握することができます。
これらの用語の意味を頭の片隅に置いておくだけで、これからの情報収集が格段にスムーズになるはずです。

MEOは地域ビジネスの生命線。今日から始める、未来への第一歩
MEOの基本について、その重要性から具体的な手法まで、ご理解いただけたでしょうか。MEOは、難しい専門知識や多額の費用をかけずとも、情熱と少しの工夫で始めることができる、地域密着型ビジネスにとって、現代で最も強力な集客ツールの一つです。
この記事を読んで、「なんだか難しそうだな…」と感じる必要は全くありません。最初から完璧を目指すのではなく、まずはできることから始めてみましょう。
あなたのビジネスの未来を変えるための、具体的な最初のステップはこれです。 「今すぐ、Googleビジネスプロフィールにログインし、あなたのお店の情報が古くなっていないか、間違っていないかを確認し、最新の状態に更新する」
まずは、それだけで十分です。正確な営業時間を入力する。新しいメニューの写真を一枚追加する。たったそれだけの小さな一歩が、これまで出会えなかった新しいお客様との、素晴らしい出会いに繋がっています。あなたのお店を探している未来のお客様は、もうスマートフォンの向こう側で、あなたからの情報を待っているのです。